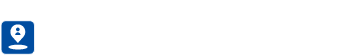HOME > お役立ち情報 > お悩み解決情報 > パート年収が130万円」を超えそうです。2年までなら超えても大丈夫って聞きますが、それって本当ですか?
パート年収が130万円」を超えそうです。2年までなら超えても大丈夫って聞きますが、それって本当ですか?
2025.08.19
 配偶者扶養に入っている場合では、年収が130万円を超えると扶養から外れる事となり、社会保険への加入が必要になります。
配偶者扶養に入っている場合では、年収が130万円を超えると扶養から外れる事となり、社会保険への加入が必要になります。
そのため、月々の手取りを減らさないように、働き方を調整する人が大勢いらっしゃいます。
こうした「年収の壁」による働き控えが懸念される中、政府は2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」なる策をを発表しました。
これについて、「2年までなら130万円を超えても大丈夫」といったことを聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、パートで年収130万円を超えそうな場合、2年までは扶養を維持できるのか、3年目に扶養内に戻せば問題ないのか、など
この制度の仕組みや注意点を分かりやすく解説させていただきます。
年収130万円を超えるとどうなるの?
扶養には「税」と「社会保険」、2つの扶養がありますが、年収130万円の壁が関係するのは社会保険の扶養です。
年収が130万円(従業員50人以下の企業に勤務している場合)を超えると、勤務先の健康保険や厚生年金に加入するか、国民健康保険などに自ら加入し保険料を負担する必要があります。
これにより、130万円をわずかに超えた場合であっても、130万円を超えなかった場合に比べ、保険料負担により手取りが減ってしまうというこということが起こります。
年収130万円は月収に換算すると約10万8333円となります。
これを超えてしまうと社会保険加入の条件適用となり、扶養から外れることになります。
そのため、多くの人が年収を130万円以下に抑えるか、社会保険料を差し引いた手取りを調整した働き方をしているのです。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容と扶養にとどまるには
少子高齢化の影響で、人手不足が深刻化している一方で、パート、アルバイトなどの短時間勤務の人が「106万円」や「130万円」の壁を超えないように労働時間を抑える傾向があります。こうした働き控えを防ぐため、政府は2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。
この制度の一部として、事業所の繁忙期や一時的な人手不足に対応するために働いた事で年収が130万円を超えた場合でも、一定の条件を満たせば配偶者の社会保険扶養にとどまれる特例が設けられています。これは、事業主が「一時的な収入超過」であることを証明することで扶養を維持できる仕組みです。
さらに、この特例措置は年1回の収入確認を前提に、同じ人について原則2回まで(最長2年まで)利用できます。つまり、一時的な収入増加と認められれば、最大2年間は年収130万円を超えても扶養を維持できる可能性があるということです。
3年目に扶養内に戻れますか? 特例利用時の注意点とは
3年目に年収を130万円未満に戻した場合は、特例措置を使う必要もなく、通常の扶養範囲内となるため問題ありません。
ただ、2年目までは特例を受ける際には手続きが必要になります。被扶養者が所属する健康保険組合などへ、課税証明書や雇用契約書といった必要書類に加え、勤務先が発行する「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」(厚労省指定様式)の提出が必要となります。
この証明書がない場合、一時的な収入超過であっても扶養から外れる可能性があります。
なお、収入確認の時期や必要書類は保険者によって異なります。例えば、毎年11月に直近3ヶ月分(例:8月~10月)の収入証明と合わせて事業主の証明書の提出が求められるケースや、年度当初からの収入が130万円を超えた時点で加入者からの連絡を求められるケースなどがあり、対応は健康保険組合ごとに異なっています。
こうした特例を利用するには、勤務先の協力に加えて、申請のタイミングや書類の準備も重要になります。手続きの詳細は、加入している健康保険組合や年金事務所にあらかじめ確認しておくと安心です。
まとめ
年収130万円を超えると、配偶者等の社会保険の扶養から外れますが、一定の条件を満たせば、特例により最長2年間は扶養を維持できます。
特例の利用には勤務先の証明書が必要であるほか、対応は保険組合ごとに異なるため、手続きの時期や内容には注意が必要です。なお、3年目に年収を扶養内へ戻す場合は、特例や追加手続きは不要です。
手取りが減ることなどを考えて働き方を調整している人は少なくないと思いますが、こうした特例や制度の内容を確認し、自分に合った働き方ができるとよいですね。